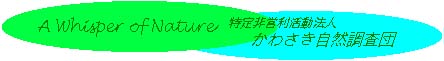
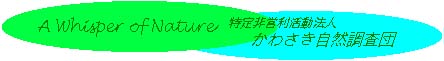
|
上の田圃、ハンノキ林の水辺保全 日 時)10月7日(火) 8:40〜12:00 晴 場 所)生田緑地 上の田圃(B06)、ハンノキ林(A07-03) 活動者)岩田臣生 
10/5(日)の里山の自然学校<脱穀>でオダ場に降りた時に、上の田圃(B06)を観察したら、水が涸れたままになっていました。 そのため、田圃の状態を調べて、湛水させるための活動を行っておかなければならないと思いました。 そこで、この日は、ハンノキ林の水辺再生活動の前に、上の田圃の下の段に水を入れるための活動を行っておくことにしました。 梅ノ木広場には、コブナグサが開花していました。 
上の田圃 私たちの田圃は、生きもののための田圃なので、基本的には、常に水がある池でなければならないと考えています。 今夏は湧水量が極めて少なかったため、谷戸の各所で水涸れが起こりました。 上の田圃も導入している水量が少なくなって、湛水が困難になったため、下の段の湛水は諦めていました。 今年は、7/22(火)に、上の段の土嚢を1枚外して、下の段にも、少し、水を入れるようにしていましたが、下の段に水面が広がることはありませんでした。 9/28(日)の稲刈りの後は、産卵に訪れるトンボのために、上の段だけでも湛水しておきたいと考えて、一旦下げていた土嚢堰を元の高さに戻しておきました。 1週間後の10/5(日)の脱穀の日には、上の段は湛水していましたが、この堰を越える水は少なく、下の段には、水面は広がりませんでした。 流量が少なくても、時間をかければ、水面が広がるかも知れないと思いましたが、全く変わりませんでした。 流れ出ている水の先端辺りに水が染み込む水漏れ穴があるのかも知れないと思って、上の田圃の下の段に入って、水漏れ穴を探しましたが、見つかりませんでした。 そこで、田圃の外周の溝を掘ってみることにしました。 掘った溝には、浅いものの、水が流れてきました。 そこで、木道側の半分、コの字状の水路を掘ったところで、この日の田圃の活動は止めることにしました。 スコップで田圃の周囲の溝を掘るのは腰の負担が大きいのです。 雨が降って、田圃に水面が広がってくれることを祈って、この日の田圃活動は終えることにしました。 10:07 暑さ指数 19.4℃、周囲温度 23.0℃、湿度 66.9%  上の田圃の下の段に掘った溝 上の田圃の下の段に掘った溝
 上の田圃の下の段 上の田圃の下の段
 上の田圃の上の段 上の田圃の上の段
ハンノキ林 生田緑地のハンノキ林はゲンジボタルの棲息地であるため、4〜8月は立ち入らないようにして、大事にしてきたことが禍したようです。 水流の泥上げが不十分で、泥が年々蓄積されてしまい、陸地化が進んでいたことが分かりました。 そのため、秋〜冬は、水流に溜まった土砂を取り出して、水辺を再生する活動を第一課題とすることにしました。 どのように展開すれば良いかは、思案中です。 この日は、ハンノキ林の(A07-02)の支谷戸の(地点01)と(地点02)の間の(地点04)の土砂を掘り出してみることにしました。 まず、ミヤマシラスゲなどの草刈りを行いました。 
それから、そこに、直径60〜70cmの穴を掘りました。 倒木は退かして、ハンノキ等の根は伐って、40cm程の深さの穴を掘りました。 30cmを越えると、崩れた飯室層と思われる土に砂が混ざったような灰色の土となり、僅かに、周囲から水が染み出してきました。 


この(地点04)の上側のハンノキの上側の水溜まり(地点01)の水は減っていました。 
下側の(地点02)に掘った穴の水は消えていましたので、そこを少し大きく掘って、水の染み出しを確認しました。 

(地点04)の穴は、もっと大きく掘らなければならないと思いましたが、手指にできたマメが破れ、腰も悲鳴を上げ始めましたので、この日の活動は終了することにしました。 辺りには、ヤブマメやカシワバハグマが咲き、コバノガマズミが赤い実をつけていました。  ヤブマメ ヤブマメ
 カシワバハグマ カシワバハグマ
 コバノガマズミ コバノガマズミ
ハンノキ林のノダケも咲いていました。 
|
 かわさき自然調査団の活動
かわさき自然調査団の活動