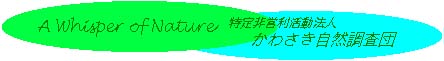
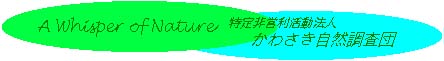
|
ハンノキ林上の池の泥上げなど 日 時)8月28日(木) 9:00〜12:00 晴時々曇 場 所)生田緑地 ハンノキ林上の池、ハンノキ林西の池、湿地地区 活動者)岩田臣生、伊澤高行、田村成美 生田緑地中央地区北側のハンノキ林地区からヨシ原地区までの谷戸は、湧水量が、今までに経験したことの無い量に減少し、至る所で、水辺が水涸れを起こして、 水辺の生きものの棲息環境としては壊滅的な状態になってしまいました。 私たち、水田ビオトープ班は、2004年以来、水辺に生き残った多摩丘陵の生きものが、将来に渡って生き続けられるように、水辺環境を保全する活動を続けてきました。 しかし、もはや、私たちの力では、どうしようもできない状態になりつつあります。 それでも、少しでもダメージを軽くしたいと思い、できることを探して、暑さに耐えて活動しています。 この日は、前回、8/26(火)に、湿地地区の水路に行った活動の結果の現状を確認してから、ハンノキ林上の池の泥上げを行い、 途中で、ハンノキ林西の池の泥上げと状態確認を行いました。 
ウェイダーを持って、谷戸に降りました。 ハンノキ林上の池の泥上げを行う前に、一昨日、湿地地区で行った水路の状態確認を行うために、ハンノキ林上の池のデッキ上にウェイダーを置いて、 ハンノキ林の状態確認を行いながら、湿地地区に向かいました。 すると、ついに、ハンノキ林内の主要な水流も、水涸れを起こしていることが分かりました。 生田緑地中央地区に生き残ったゲンジボタルはどうしているだろうか、ついに、この谷戸から消えてしまっただろうかという心配に、 活動意欲が押し潰されてしまいそうになりました。 ハンノキ林内の水流が涸れたのですから、当然のことですが、一昨日、掘り直した水路に水はありませんでした。 田圃通信だけでは不十分と思ったので、この水路の変更について、考え方など、現地説明を行いました。 ハンノキ林上のデッキに戻って、ウェイダーを履いて、ハンノキ林上の池に溜まった泥を周囲に上げる活動を始めました。 冬のうちから、常に、水が黄色に濁っていたので、これでは、生きものの棲息は困難と思い、水質を改善する活動を行わなければならないと思いながら、 手がまわりませんでした。 夏期はホトケドジョウなどの湧水に依存する生物が集まっているはずの池ですが、早い時期から、水流が途切れてしまったので、 ここまで遡上できた生物は少ないだろうと思います。 
10:02 WBGT 23.8℃、周囲温度 27.9℃、湿度 64.6% 活動前にトラップに入っていたアメリカザリガニは 5匹でした。 活動中に捕獲したアメリカザリガニは 10数匹で、これはエサとしてトラップに入れました。 






ハンノキ林上の池の泥上げが進んだところで、ウェイダーを履いているついでに、ハンノキ林西の池の状態観察も行うことにしました。 この池には、当歳魚を含む多数のホトケドジョウが、量は少ないながら、水温の低い流入水に向かって、集まっていました。 そこで、溜まった泥を水漏れ穴があった辺りを中心に、堤体上に上げる活動を行い、水深を深くしました。 この池は、湧水に依存する生物の避難場所になっていることを確認できました。 また、谷戸の水辺に、いくつもの小規模な溜め池的な機能を持つ池を配置することを考えるなら、一つの候補地になると思いました。 ここなら、生きものが下流域と往来できる状態にしながら、谷戸の奥の溜め池的な機能を持たせることができそうです。 

ハンノキ林上の池の泥上げも進んで、コロイド状態だった泥を上げることができましたので、水深30cm程度の水域をつくることができたと思います。 水は酸欠気味なのか、5cm大程のホトケドジョウが数匹、水面近くを泳いでいました。 


暑い夏には行いたくない活動でしたが、湧水減少については、少なくとも、ホトケドジョウが消える事態にはなっていないことが確認できました。 問題は、ゲンジボタルですが、これは、迂闊な調査はできません。 |
 かわさき自然調査団の活動
かわさき自然調査団の活動