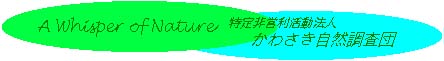
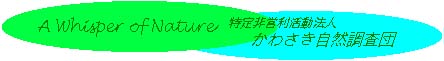
|
夏の生物多様性保全の活動 日 時)8月21日(火) 9:00〜12:00 晴 場 所)生田緑地 ハンノキ林源頭部自然探勝路、ハンノキ林西の池、湿地地区、上の田圃地区、下の田圃地区 活動者)岩田臣生、伊澤高行、田村成美 生田緑地で活動している皆さんでも、生田緑地の今夏の水不足を感じている人は殆どいないと思います。 生田緑地の湧水が、不透水層である飯室層の上に堆積した関東ローム層に貯留された雨水が染み出してきた水であることを理解している皆さんなら、 貯留可能量が如何に少ないかを想像できると思います。 そして、夏は植物が消費する蒸散量が多いことも想像できると思います。 出て行く量の多い夏に、降雨が少ない、入ってくる量が少ないのですから、湧水のつくる水流は涸れる所だ出てきます。 その湧水を頼りに生活している水流の水辺の生物にとっては、命の危機でもあります。 水田ビオトープ班では、夏の渇水期にも、水辺の生物が生き続けられるように、水流を連続する水溜まりにする水辺保全活動を続けています。 生田緑地のような急峻な地形の水辺では、流れ易い状態にしてしまうと、渇水期には完全に水面が消えてしまいます。 そこで、渇水期にも、小さな水面が残っている状態にしようと考えての水辺保全です。 しかし、それも、今夏は限界を超えたのではないかと思い始めています。 このまま、降雨が無ければ、谷戸の水辺の生物が消えていくことが想起されますので、雨が降るまでの間、水道水を分けてもらえないかとまで考えてしまいます。 最近の活動は、僅かの水を少しずつでも、必要な範囲に分けて、その範囲の生きものの命を守る方法を試しています。 普通に水辺保全活動ができない状況のために、この日も、下図に赤線、赤丸で示したような場所での活動となりました。 
(ピクニック広場のトモエソウ保護) トモエソウは、植物班の佐藤班長によれば、川崎市内では生田緑地にあるだけだそうです。 ということは、生田緑地ピクニック広場のトモエソウだけということになってしまったようです。 トモエソウは、オトギリソウの仲間で、神奈川県植物誌によれば、県内に広く分布しているが、個体数は多くないとあります。 多年草ですが、放置すると周囲の植物に負けて消えていくのかも知れません。 私たちは、種子を採取しておいて、プランターで発芽させて、その苗を補植してやるようなことを、時々、行っています。 観察していると、追加した苗の方が元気が良いので、この場所にあり続けさせるためには、数本の追加を続ける必要がありそうです。 丁度、周囲の植物が繁茂する季節で、全体が覆われてしまっていたので、少し雑な草刈りを行いました。 実もあったので、これが成熟したら、採取して、苗をつくって、補植したいと思います。 また、ここは木陰で暗いので、どこか陽当たりの良い場所に植えてみることも考えたいと思いました。 

(ハンノキ林源頭部の自然探勝路の植物保護) ハンノキ林源頭部、ハンノキ林と萌芽更新地区の境界となる自然探勝路のアズマネザサ刈りを、一昨日、8/19(火)に行いました。 ここには、オトコエシが大きく育っていて、間もなく開花時期となるところでした。 萌芽更新地区の花には、ツチバチの仲間や、アサギマダラが吸蜜に訪れていました。 この場所でも開花すれば、吸蜜源となるはずです。 ただ、谷側に向いて、茎を伸ばしていたので、来園者に折られないように、太めのアズマネザサを伐って来て、保護柵をつくりました。 また、ハナイカダ?の実生にも、保護柵をつくりました。 

9:41 WBGT 25.6℃、周囲温度 30.5℃、湿度 58.4% 

(ハンノキ林上の池) ハンノキ林上の池は、最近は、常に濁っていて、水質悪化が心配されていました。 初夏には見られたヤブヤンマにも、今年は出会えませんでした。 様々な原因が考えられますが、私たちとしては、谷戸の最奥の湧水による池として保全し、ホトケドジョウやカワニナなどが越冬できる池にすることだと思います。 そこで、長らく行っていなかったアメリカザリガニの駆除から始めてみようと思います。 池の近くに放り出しておいたアナゴカゴが使えるかどうかは分かりませんでしたが、 手網を使って、アメリカザリガニを10匹ほど採集し、これを、アナゴカゴに入れて、池の中に置いてみました。 池には泥が溜まって、すっかり浅くなっていました。 今日は、伊澤が泥上げをすると言って、肥柄杓を持って降りているので、後で、状態が分かると思います。 楽しみです。 
(ハンノキ林西の池) ハンノキ林西の池も調べておくことにしました。 堤体の一部に大きな穴が開いていて、そこに池の水が、少しずつ流れ込んでいる様子でした。 池に流入する水量は、流れているのか判断するのが困難なぐらい少ない状態でした。 池の水位としては、涸れそうという感じはありませんでした。 ただ、この池は、オニヤンマやホトケドジョウなどの生きもののことを考えなければならない水辺です。 つまり、水温が問題です。 この流量で水深が浅いと、水温が上がってしまうと思います。 堤体にあった水漏れ穴は泥で塞ぎましたが、できるだけ早く、溜まった砂泥を掘り上げて、水深を深くしてあげなければならないと思います。 
(湿地地区) 湿地地区は、導入している水路に、また水漏れ穴が開いていたので補修したと聞きましたが、 水涸れしてからの水草の状態を観察しておくことにしました。 水草が枯れても、何とか種子を少しは残せそうです。 
(上の田圃) 上の田圃は、導水路の泥上げを済ませたとのことで、非常に僅かながら、水が流れていました。 そして、1段目には水面が広がっていましたが、2段目は完全に涸れていました。 稲穂は、1段目も、2段目も、結実して、重くなり始めているように見えました。 下の段の湿った土の中にも、生きものが残っている可能性があります。 悩みましたが、1段目の土嚢堰の土嚢を1枚外して、少しながら2段目に水を落としてみました。 後は、雨が降ってほしいという神頼みです。 (下の田圃) 下の田圃も、土嚢堰からの水音が聞こえませんでした。 ただ、植物は、まだ元気でした。 
気持ちが諦めてしまっているので、状態観察も止めることにして、戻り始めたら、樹陰に、ゴマダラチョウが飛んで来ました。 慌てて、シャッターを押しましたが、・・・。 
ハンノキ林上の池に着いたら、伊澤さんが肥柄杓を使っていました。 

早めに活動を止めて、帰ることにしました。 萌芽更新地区下の園路沿いに、翅を傷めて、上手く動けないタマムシがいました。 
ピクニック広場で、少し休んでから帰りました。 11:29 WBGT 26.7℃、周囲温度 30.1℃、湿度 68.3% |
 かわさき自然調査団の活動
かわさき自然調査団の活動